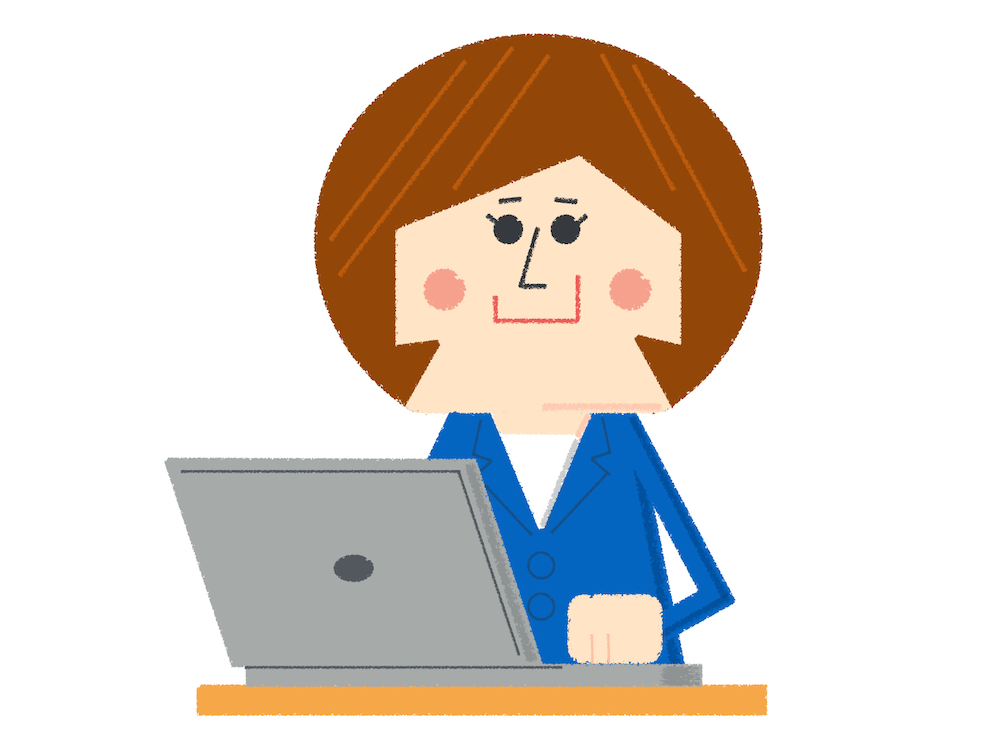1,税理士の分類について
税理士と言えば、確定申告などの書類作成や税務相談といった、税に関する専門的な知識を生かしてさまざまなサービスを提供する専門職です。
身分はあくまでも民間人ですが、国家資格がないと開業することができず、職務についても法律で細かく規定されているため、非常に公的な性格の強い職業であると言えます。
税理士として業務に従事するには、大きく分けて2つの方法があります。
1つは自ら税理士事務所を開業することで、もう1つはすでに開業している税理士事務所に就職することです。
この他には、弁護士事務所や司法書士事務所などの隣接する専門職の許で働くというバリエーションもありますが、先の2つに比べると数はそれほど多くありません。
自ら開業するにせよすでに開業している事務所に就職するにせよ、従来、それらの事務所は個人事業所に限られていました。
通常、民間の事業者が開業する場合は、一定の要件を満たせば原則として業種に関係なく株式会社や合同会社などの法人格を取得することができます。
一方、税理士の場合はこれまでは個人名義での開業のみが許されてきました。
しかし2001年の税理士法改正によって、現在では税理士事務所も一定の要件を満たせば法人になることが認められるようになっています。
これを、税理士法人と言います。
2,税理士法人とは
税理士法人は、営利法人で言えば合名会社に似たスタイルを採用しています。
すなわち、2名以上の社員が出資し、合同で事務所を設立する形式となります。
この時、社員は全員が税理士であることが条件です。
そして、登記を行うことによって法人格を有することを第三者にも主張できるようになります。
法人格を取得すると、事務所の名称が「何々税理士事務所」から「何々税理士法人」に代わります。
ただし、業務の内容には一切変更はありません。
各種申告や申請の代理、税務関係書類の作成、税務に関する相談対応など、税理士として行うことのできる業務の範囲はまったく同じです。
3,個人の税理士事務所と税理士法人との違い
では、個人の税理士事務所と税理士法人とではどのような点が異なるのかというと、組織のありようです。
法人格を持つことで、個人事務所では認められなかったさまざまな権利が新たに発生することとなります。
その1つが、支店の設置です。
法人格を有すると、主たる事務所の他に支店を開設することができるようになります。
ただし、無制限にではありません。
それぞれの支店には1名以上の税理士を配置することと定められているので、在籍する税理士の人数が設置できる支店の数の上限ということになります。
支店を設置できるということは、個人事務所よりも営業エリアが広くなることを意味します。
そのため、積極的な事業展開が行えるというメリットがあります。
また、たとえば各地に営業拠点や関連会社を持つ企業を取引先に持つ場合、その事業所ごとにそれぞれの支店が顧問契約を締結すれば、業務の一貫性が保てるという利点ももたらされます。
法人格を持つことで備わる組織的な特徴としてはもう1つ、事業主体としての継続性を挙げることができます。
個人開業の事務所の場合、代表者である税理士が廃業すれば原則としてその事務所も廃業することになります。
仮にそこで勤務していた別の税理士が後を引き継いだとしても、それば別の事務所と位置づけられます。
しかし、法人であれば、代表者の交替があったとしても法人格はそのまま継続します。
もちろん登記事項の変更といった手続きは必要ですが、事業主体そのものには何ら変更がありません。
このことは、法人格を持っていれば顧客側からは長期にわたって安定した関係を築けるという評価を得やすくなることを意味します。
顧問先もまた株式会社等の法人格を有しているのであれば、この安定性は大きな強みとなります。
その他、これは税理士業務に限らずあらゆる業態について言えることですが、法人格を持つことによって個人事業所とは異なる法令上の扱いを受ける点もいくつかあります。
その1つが税法上の取扱いです。
個人事務所であれば、そこで発生する所得は当然ながら個人所得税の対象となりますが、法人であれば税率のより低い法人税や事業税の対象となります。
また、認められる経費の範囲も総じて個人事務所より広くなります。
税理士と言えば節税対策の相談を受けることも珍しくありませんが、法人化によって自ら節税することが可能です。
また、社会保険の取扱いも法人化によって変化します。
個人事務所の場合は自らが事業主体となるので、被用者を対象とする健康保険や厚生年金には加入することができません。
しかじ法人であれば代表者もまた事務所に使用される者と見なされるので、強制加入の対象になります。
なお、法人化は事業に継続性がもたらされることが特徴だと述べましたが、当然ながら解散することもあります。
税理士法人は、株式会社が解散する場合とほぼ同様の手続きによって、自ら解散することができます。
また、裁判所から解散命令を受けることもあります。
最終更新日 2025年6月18日 by preserving